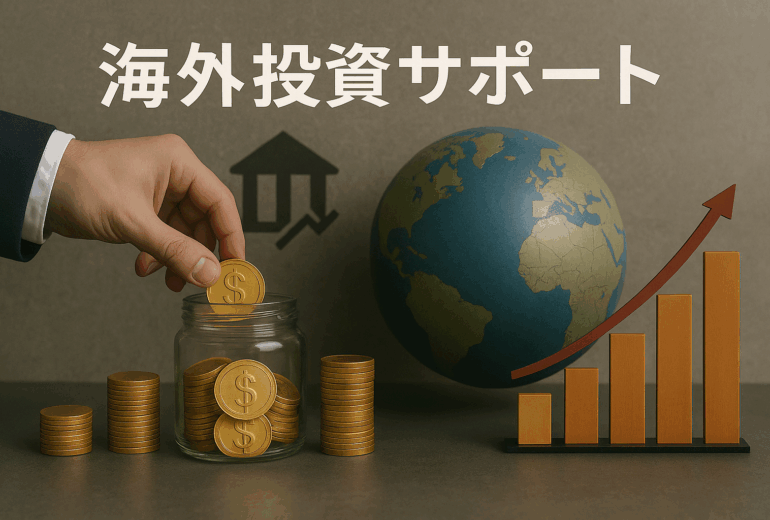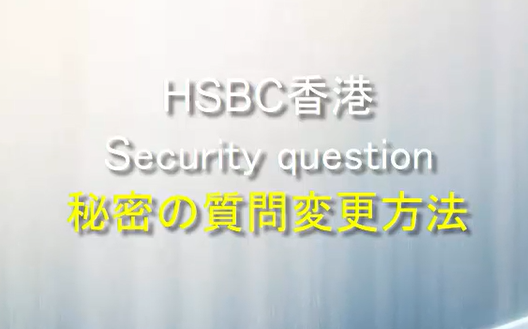覚えておきたい銀行に関する大切なこと
基本的に香港のHSBCに関する情報を発信しているこのカテゴリーですが、
今回は銀行口座全般に関する
非常に重要な件についてお伝えしていきたいと思います。
海外投資をしているしていないにかかわらず、
海外の銀行口座を保有されているのであれば
本日お伝えする内容は、
口座保有者だけではなくご家族にも関係してくることなので
「そういえばうちの旦那、海外の銀行口座持ってたわ」
という奥様や
「たしかうちの奥さん、海外の銀行がどうの言ってたなぁ?」
というご主人様も
今回の内容はしっかりと目を通されることをお勧めします。
この内容は、
今月の28日に開催いたします
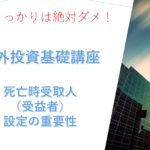
今年2回目となる本セミナーのご案内です。 前回の開催では、ご参加いただいた皆さまのご契約内容に関する理解が、 想定以上に不十分であることが浮き彫りになりました。 特に、ご契約時に商品のメリットばかりが強調され、 リスクや万が一の際の対応について、十分な説明を受けていない、 あるいは内容を忘...
このセミナーとも関係しておりますので
受講申し込みをされている方には必ず読んでいただきたい内容です。
そうです、今回この記事でお伝えするのは
口座保有者がお亡くなりになってしまった場合のお話です。
ある一定の年齢の方であれば経験されたことがあるかもしれませんが、
邦銀であったとしても口座名義人がお亡くなりになってしまった場合に
口座の残高を引出しするのはかなりの労力を要します。
実際わたしも昨年、一昨年とで両親が他界しましたので
その苦労は経験済み。
そうは言っても、国内の銀行ですので
面倒ではありますが時間をかけて準備を整えさえすれば
費用はかけずに口座内のお金は引出しすることは可能です。
ただ注意しなければならない点がいくつかあります。
名義人が亡くなっているのに家族が勝手に引き出してしまうと
様々な問題があるという事です。
お伝えした通り最近自分の身に起きたことなので
いろいろと調べましたのでその内容もシェアします。
※私個人は資格を有しておらず、調べた内容がすべて正しいものとは限りません。
全てを鵜呑みにせず、あくまでも個人で調べた結果であることをご理解の上お読みください。
前提として相続人が一人だけなのか、複数いるかによって変わってくるとのことです。
相続人が自分ひとりの場合
法律上の位置づけ
・亡くなった時点で、預金や不動産などの資産は全て自分の資産となる。
・法律上は自分の資産であるため、他人の取り分を侵害しているわけではない。
引き出した場合の刑事責任
・窃盗罪や横領罪といった刑事責任を問われることはほぼない。
※ただし、ATMカードで勝手に引き出すと銀行規定違反となります。
民事上の問題
・親に借金があった場合には「単純承認」となり、借金全てを相続したものとみなされる。
実務的なリスク
・親の死亡届が提出されると役所から銀行にも情報が伝わり、口座が凍結される。
・凍結前に引出ししていても、銀行から相続手続きをするようにと連絡が来る。
・ATMカードで勝手に引出しをしていると「不正利用」と認定される。
相続人が複数いる場合
法律上の位置づけ
・亡くなった時点で、預金や不動産などの資産は全て相続財産となる。
・その財産は、遺産分割が終わるまで相続人全員の共有財産となる。
引き出した場合に問われる可能性がある罪
①窃盗罪(刑法235条)
・遺産は相続人全員の共有資産。
・他人の持ち分が含まれる財産を引出しすると窃盗罪にあたる場合がある。
・罰則:10年以下の懲役または50万円以下の罰金。
②横領罪(刑法252条)
・資産を補完する立場にある人(通帳やカードを預かっていた)が、勝手に使った場合横領罪に問われる場合がある。
・罰則:5年以下の懲役または50万円以下の罰金。
③有印私文書偽造・同行使罪(刑法159条)
・親が生きているかのように装い引き出した場合や、虚偽の書類を作成した場合、文書偽造罪が成立。
・罰則:3か月以上5年以下の懲役
民事上の責任
・刑事責任とは別に、その他相続人から不当利得返還請求や損害賠償請求を起こされる場合がある。
・遺産分割の場で、勝手に引き出した分は相続財産から差し引かれる場合がある。
よくある誤解
・自分も相続人だから少しぐらい引出ししても大丈夫。
⇒取り分が確定していないため、その他相続人の財産を勝手に使ったことになる。
・親に生前、自由に使っていいと言われていたから問題ない。
⇒口約束は無効。遺言書がなければ法定相続ルールが優先される。
調べておいて本当によかった!と思ったのは言うまでもありません。
というように、
上記のような注意点があることを頭に入れておいてください。
これは、国内外にかかわらず共通するものとお考え下さい。
海外の銀行を例に挙げると、
HSBCなどのATMカードの在処を知っていて
PIN6桁もわかるからと言って勝手に引き出して使ってしまったり、
インターネットバンキングのログイン情報を知っているうえに
スマホアプリも使用できるからと言って
勝手に自分の銀行口座へ送金などしようものなら。。。
わかりますよね?
海外だから大丈夫だろうと思っている方がいるかもしれませんが、
現在はCRS加盟国の資産情報は国内に筒抜けだと思っておく方が無難です。
「Common Reporting Standard」の略で、国際的な税務情報交換の基準を指します。
これは、経済協力開発機構(OECD)が策定したもので、
各国が税務関連情報を自動的に交換するための枠組みを提供し、
脱税や資産の隠蔽を防ぐことを目的としています。
日本では、平成30年からCRSに基づいた情報交換が開始されており、
外国の金融機関にある口座情報が国税庁に送られています。
CRS加盟国一覧
ここで間違ってほしくないのは、
決して海外の銀行口座が「悪い」「必要ない」という考えにはならないでください。
今までもこれからも国際社会を生き抜いていくためには
非常に重要なアイテムであることには変わりなく、
国内で抱える問題がさらに進むことを考えると
持たざるリスクを考えたほうが良いと私たちは考えています。
では、そろそろ本題に入りましょう。
お伝えした通り基本的な考え方は同じということなので、
勝手に使うようなことはやめておきましょう。
そして、海外であることからその国の法律や銀行ルールに従った
相続手続きが必要になります。
多くの国で求められるのは、以下の書類がベースだとお考え下さい。
・死亡証明書
・戸籍謄本
・相続人の証明書
・遺産分割協議書
そしてすべての書類に関してそのまま提出することはできず、
翻訳と認証などが必要になってきます。
今回は香港の銀行について重点的にお伝えしていきますが、
その他の国の銀行にも共通する事柄が多くありますので
参考にしていただけるかと思います。
基本的な考え方
・日本に住む日本人が亡くなった場合、その遺産は日本の民法に基づき相続する。
・ただし、財産が香港にある場合には香港の銀行規定と法律に従った手続きが必要。
・つまり「日本の相続法+香港の銀行実務」をクリアする必要がある。
香港の相続手続きの特徴
香港の場合には英米法系の制度があり、プロベート手続きが基本となる。
・遺言書がある場合:
⇒遺言を香港の裁判所(High Court Probate Registry)が確認し、
Grant of Probate(遺言検認許可証) を発行。
・遺言書がない場合:
⇒法定相続人が裁判所に申請し、Grant of Letters of Administration(遺産管理許可証) を取得。
//重要//
「Grant」(認可文書)を銀行に提出しないと、口座は解約できず、預金を相続人に移せません。
必要書類(あくまでも典型例)
銀行から請求される書類は銀行ごとに異なるため、一般的なものを紹介。
-
死亡証明書(日本のもの+英訳+認証済み)
-
戸籍謄本(相続人を証明するため、英訳+認証/アポスティーユ)
-
遺言書(あれば)+検認証明
-
遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)
-
相続人全員のパスポートや住所証明
-
香港裁判所発行の Grant of Probate / Letters of Administration
//重要//
「日本の公的書類はそのままでは使えない」
翻訳+公証人認証+外務省アポスティーユ+香港側での認証 が必要になります。
手続きの流れ(あくまでも典型例)
1・国内で死亡届、戸籍整理を済ませる
2・必要書類を翻訳+公証+アポスティーユを取得
3・香港の弁護士を通じて、裁判所(High Court Probate Registry)にプロベート申請
4・裁判所からGrant (認可文書)が発行される(数か月〜1年程度)
5・Grantを銀行に提出し、相続人に払い戻し
実務上の注意点
・時間がかかる:最短でも一年以上かかると思っておく必要がある
・費用が掛かる:香港の弁護士費用、公証、翻訳費用などを含めると200万円以上はかかる
・銀行毎のルール:預金額が少額な場合、銀行によっては「簡易払い戻し手続き」ができる場合もある
ではこのあたりで、
気になっているであろう用語を解説しておきたいと思います。
<<用語解説>>
アポスティーユ(Apostille)とは?:
海外で日本の公文書を公式に使用するための証明書になります。
・1961年ハーグ条約(Apostille条約ともいう)に戻づく制度
・加盟国間では、大使館・領事館での追加認証が省略できる
・外務省や法務局が発行する「証明スタンプ」付き書面がアポスティーユである
要は、この書類は本物であり、日本の役所が発行したものであると国際的に保証する仕組み。
プロベート(Probate)とは?:
主にイギリスやアメリカ等の英米法圏でおこなわれる
無くなった人の遺産を裁判所が監査して整理・分配する手続きになります。
プロベート手続きでは、以下の内容を確認・承認します。
・遺言書の有効性を確認
⇒遺言書が法律に則って有効であることを審査
・遺産の把握と評価
⇒預金・不動産・株式・借金といった財産全てを洗い出し、価値を算定
・債務や税金の清算
⇒故人が残した借金や税金を支払う
・残余財産の分配
⇒相続人や遺言の受益者に対して正式に分配
香港でプロベート手続きを行うための必要書類:
・香港の裁判所が発行するGrant of Probate(遺言検認許可証) または Letters of Administration(遺産管理許可証)
・死亡証明書(英訳+公証+アポスティーユ)
・戸籍謄本(相続人を証明、英訳+公証)
・相続人全員の身分証明書(パスポートなど)
・遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
※プロベートを行うには香港の弁護士に依頼する必要があり、
その費用が高額になっている。上記で200万以上との金額があるが、
弁護士への報酬だけで200万円を超える事もある。
ここで既にお分かりかと思いますが、
タイトルにある、「驚くほど高額なアレ」とは、
プロベートにかかる費用というわけです。
ではどのように回避することができるのでしょうか?
日本人が香港で相続する際、少額の相続財産に対して、
「簡易払い戻し手続き」で対応できる制度があります。
少額の預金であればプロベートを省略できるということです。
大まかではありますが、
私なりに調べた内容をお伝えします!
知っておいて損は無いお得情報かと思いますよ!
香港における「少額相続財産(Small Estate)」の簡易制度
1.Confirmation Notice(確認通知)制度
対象となる財産:
相続財産が香港に残された現金のみで、合計が5万香港ドル(約100万円)以下である場合に適応される。
ただし被相続人が信託財産を持っていたり、「Tso」「Tong」の管理者である場合は対象外。
※「Tso(祖堂)」「Tong(堂)」はいずれも香港や広東地域に伝わる一族・宗族の共同体組織を指す概念です。
中国南部の伝統的な社会構造の一つであり、特に香港の不動産や相続に関するものです。
制度の概要:
Home Affairs Department(香港内務省)のEstate Beneficiaries Support Unitに申請し、
Confirmation Noticeを取得することで、通常必要なGrant of Probate(遺言検認許可証)や
Letters of Administration(遺産管理許可証)無しで財産を取り扱える可能性がある。
必要な書類・手順:
・所定の申請フォーム(例:HAEU5=遺産が全て現金で構成され、その合計が50,000ドル以下であると認定する確認通知書の申請書)
・財産が5万香港ドル以下であることを宣言するアフェアデービス(法的宣誓分)
・財産の詳細を記載したSchedule(一覧表)
・書類審査後、12営業日以内に通知書が発行されることが多い。
※Confirmation Noticeは「Grant of Representation(検認・管理許可証)」の代わりにはなりますが、
必ずしも銀行がそれに従う義務があるわけではありません。
最終的にはそれぞれの銀行が裁量で支払いに応じるか判断することになる。
2.Estate Duty(相続税)について
2006年2月11日以降に無くなった方の相続財産に対する相続税は廃止されている。
ただし、不動産を相続する場合には印紙税の対象になることがあり、
別途税務上の書類が必要になる。
【重要】
HSBCは、原則として香港裁判所発行のGrant無しには支払いに応じない立場のようです。
ただし、HSBCの公式ガイドラインによると
預金総額が5万香港ドル以下の場合、Confirmation Notice を受け入れる可能性があります。
とは言いつつも、最終的に銀行の裁量で払い戻しの可否を判断することになるため
Confirmation Noticeを持って行っても「対応できない」となる場合もあるため注意が必要。
という事で次に行きましょう。
共有名義
HSBCの共有名義(Joint Account)の場合には、
サバイバーシップ方式が適用されるため、基本的には生存している共有名義人に
自動的に移転される。
ただし、銀行が一時的に口座を凍結する場合もあり、その場合には証明書類の提出が必要。
証明書類:
・死亡診断書(英訳+公証人認証+アポスティーユ)
・遺言書がある場合(コピー+翻訳、公証)
・生存名義人の身分証明書(パスポート)
・住所証明書(国際免許証、銀行の英文statement)
・関係証明(戸籍謄本、英訳+公証+アポスティーユ)
※共有名義はサバイバーシップ(生存者への自動継承)の原則があるため、
通常は関係証明まで要求されないケースが多く、死亡証明書+生存名義人の確認書で済むこともあります。
【重要】
残念ながら、現時点で既に共有名義になっている必要があり
日本居住者の場合には後から共有名義人を使いすることはできなくなってしまいました。
ここまでいろいろとお伝えしてきましたが、
一番確実は回避方法は、
『生前に送金できる預金は全て国内へ送ってしまうこと。』
これに限るという事です。
その際の注意点をお伝えします。
・スマホアプリは必須である。
・Time Deposit(定期)を組んでいる資金は動かせない。
・送金にはいくつかの手数料が発生するため口座をカラにするのを避け
ある程度残る額を送金したほうが良い。
なお、今回のブログの内容につきましては
ご質問いただきましてもご回答することができませんので
予めご了承ください。
ただし!もうすでに名義人がお亡くなりになってしまわれた
という場合には、
上記の内容をご確認いただいたうえで、
口座資金が一定額以上あるという場合には
香港の弁護士をご紹介することも可能ですので
ご相談ください。
また銀行口座ではなく、
フレンズプロビデント、RL360、インベスターズトラスト等といった
海外の商品をご契約されていたご家族がお亡くなりになってしまわれた場合にも
お手伝いが可能な場合もございますので、
心中お察しいたしますが一度お気軽にご相談ください。
どこの商品を契約されていたのかが分かれば
お役に立てるかと思います。